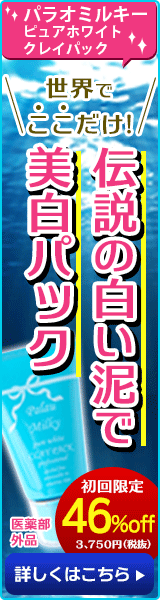乳酸菌は相性の良い菌しか生き残れない。

人の腸内細菌の組成は生後1年間で大半が
決まってしまうと前項でお話しました。
では、なぜ生活習慣によって腸内バランスが乱れたり
悪玉菌が優勢になったりするのでしょうか。
腸内細菌の最大勢力は「日和見菌」であり、
善玉菌と悪玉菌は少数派です。
腸内バランスのカギを握ってるのは「日和見菌」です。
日和見菌は有利なほうに味方しようと様子を伺う
性質があり、腸内細菌の全体像は生後1年が
過ぎると変わらなくなりますが、善玉菌と悪玉菌は
拮抗しながら変動を繰り返しています。
日和見菌はその変動を見てどちらに着くかを決めて
良い働きもすれば悪い働きもするのです。
なので、日和見菌が善玉菌の味方に着く様に、
善玉菌を活性化させる食事や生活を習慣化出来れば
最大勢力の「日和見菌」は勢いのある善玉菌の味方を
させ、善玉化でき腸から健康な心身をつくっていけます。
その為にも、少数派の善玉菌を毎日サポートする
食習慣が必須なのです。
善玉菌を増やすには生きた善玉菌を腸に取り込むか
すでに居る善玉菌に好物を与え増殖させるかになります。
腸に取り込む健康法は「プロバイオティクス」と方法で・・・
健康の為にヨーグルトを食べる人は多いですが、これも
「プロバイオティクス」です。
善玉菌の代表である「乳酸菌」はヨーグルトに豊富に
含まれているからですが・・・
残念ながら通常のヨーグルトにいる乳酸菌は胃酸に弱く
約9割が「胃」で死んでしまいます。
そこで人気なのは「生きて腸まで届く」というヨーグルトです。
ここでも落とし穴があります。
善玉菌の乳酸菌は菌の種類の総称で仲間には・・・
ビフィズス菌
ブルガリア菌
カゼイ菌
など多種多様な菌がいて、どの菌が合うかは人によって
相性が違うのです。
腸粘膜の表層は「ムチン層」という膜で覆われています。
この「ムチン層」に「乳酸菌」はくっつき腸粘膜を酸性に
保っています。
多くの病原菌は酸性の場所では活動出来ませんが・・・
乳酸菌のついてない部分には病原菌が付着でき、
思いのままに悪さが出来るのです。
なので・・・
腸内の乳酸菌を増やしてムチン層を守る事が、
病原菌や有害物質から腸を守る事になるのです。
「ムチン層」はA型の人はA型の血液物質から、
B型の人はB型の血液物質から出来ています。
「ムチン層」に付着できる乳酸菌はこの血液物質
と相性のよい菌のみです。
白血球の形や体質、生後1年間の生活環境など
によっても、乳酸菌との相性は決まります。
相性の合わない菌はどんなに良い働きをする菌でも
腸に棲みつけず3〜7日で排便されてしまいます。
腸内には赤ちゃんの頃にすみついた元々の菌達が
いて、見知らぬ菌は侵入者とされ排除されてしまう
のです。
これも免疫システムの一つで腸の環境を乱れさせない
ためなのです。
「プロバイオティクス」の実践は口でいうほど簡単では
ないのです。
ただヨーグルトの乳酸菌の9割が胃酸で死んでしまっても、
免疫システムに排除されてしまっても・・・
乳酸菌が生きていた「溶液」は腸で生息している善玉菌
のエサになり古参の善玉菌を元気づけるので、腸にとって
良い食べ物であるのは変わりません。
なので、安直に新たな善玉菌を送り込むよりも・・・
「自分の腸内にいる善玉菌をいかに育てるか」に
重点をおいて・・・
TBS「駆け込みドクター」で池谷敏郎医師が
注目のスーパーフードで一押した「菊芋」や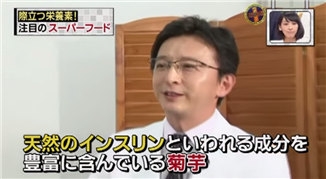
NHK「ためしてガッテン」で
日本内分泌学会会長であり、
慶応大学医学部の伊藤 裕 教授が,
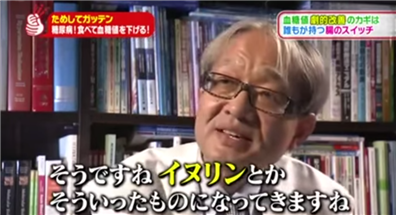
ペットに毎日ごはんをやるように腸内細菌にも毎日
「イヌリン」など水溶性の食物繊維をエサとして
育てる効果を説明している事を実践し・・・
古くから、日本人の腸に良いと伝えられてきた
味噌、しょうゆ、酢、納豆、ぬか漬けなどの
「発酵食品」をうまく食生活に取り込んで行く
事が・・・
腸内細菌を育て、その菌に私たちの健康を
守ってもらうと云うのが、腸そして体全体に
とっての一番の「秘訣」なのです。